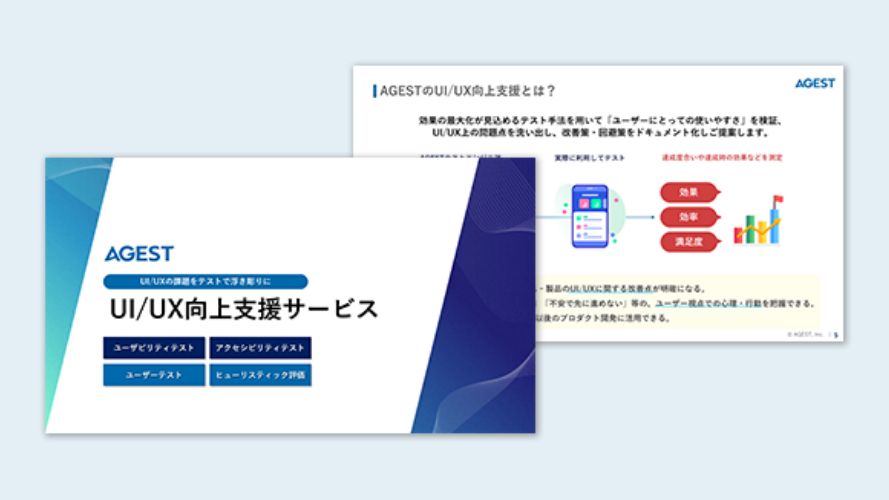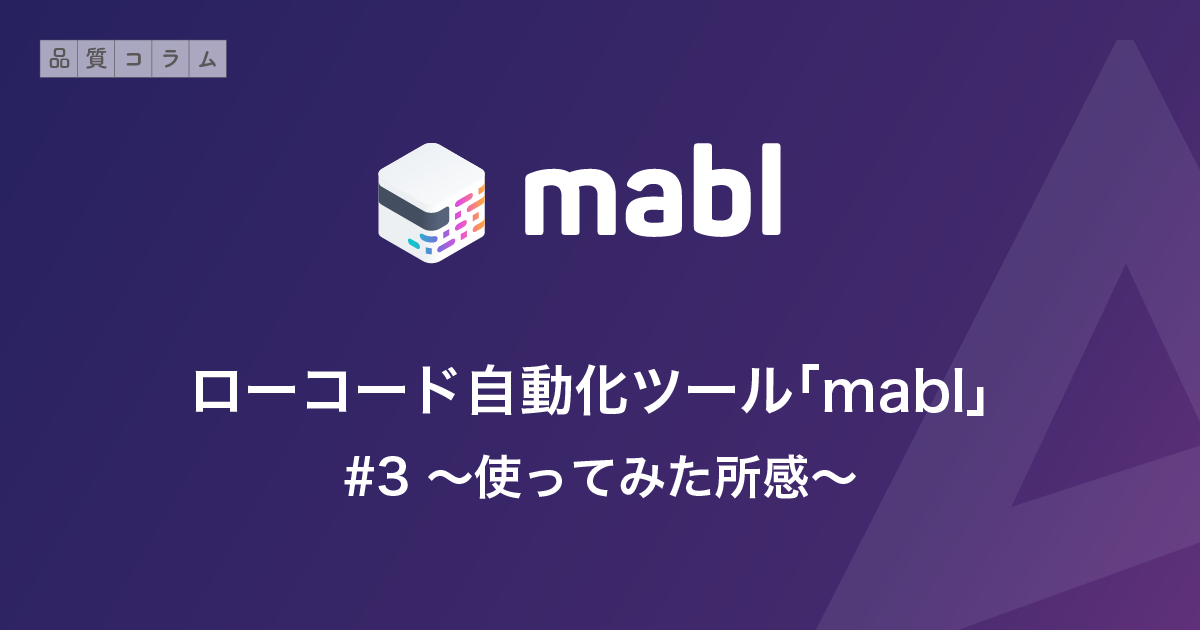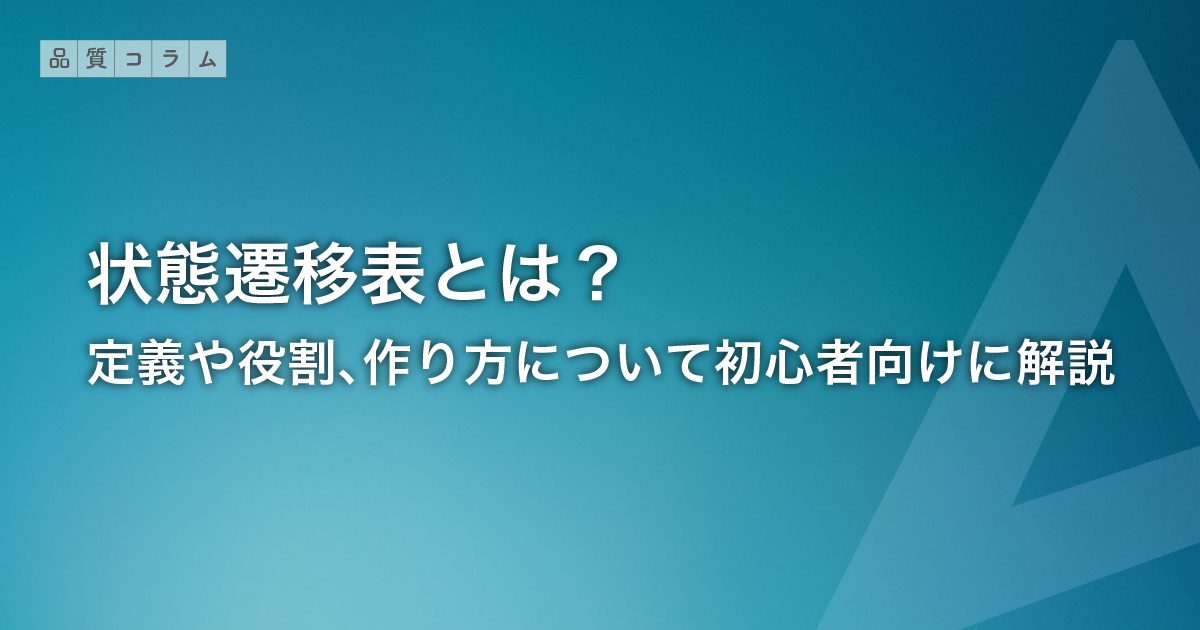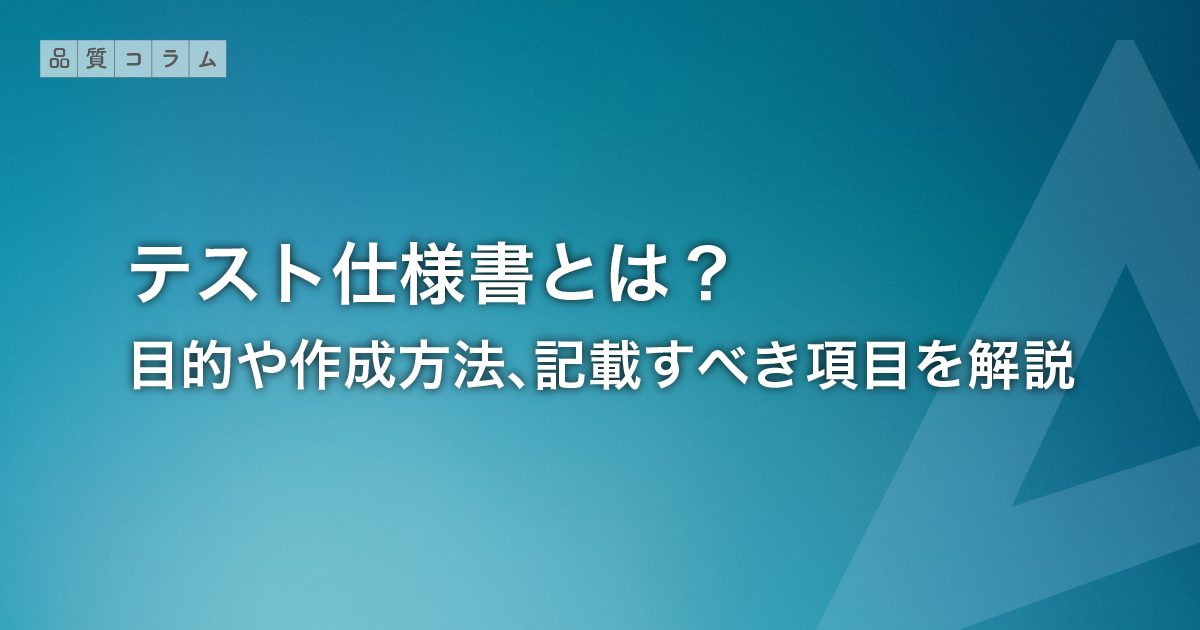公開:
ユーザビリティテストとは?定義や目的、手法別の実施のポイントを解説
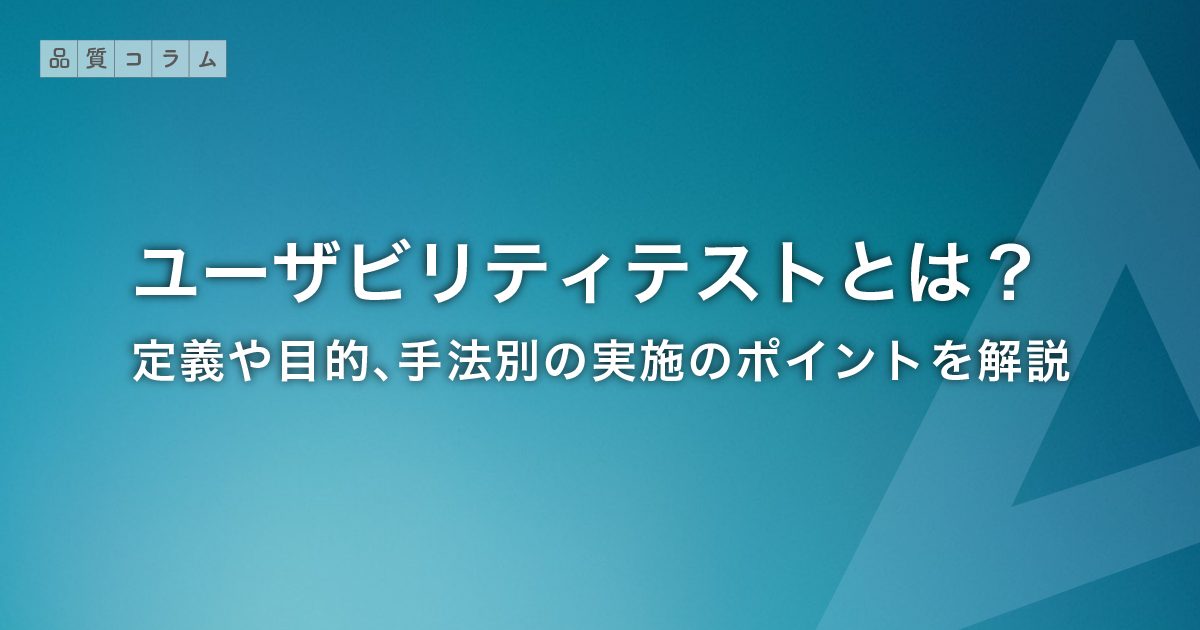
自社プロダクトのUI/UXに課題を感じながらも、ユーザー視点に立った評価や改善に苦労する企業は少なくありません。
こうした問題の解消に向けて実施されるのが、ユーザビリティテストです。このテストでは、対象ユーザーに近い人物に実際の利用シーンを想定して操作してもらうことで、画面の見やすさや導線のわかりやすさなどを評価・分析し、改善につなげていきます。
本記事では、ユーザビリティテストの定義やほかのテスト手法との違い、評価方法、改善のプロセスまでを解説します。自社にとって適切な進め方を考えるうえでの参考にしていただければ幸いです。
開発プロジェクトにおける『第三者検証』の重要性とは│資料ダウンロード
目次
ユーザビリティテストとは
まずは、ユーザビリティテストの定義や実施の目的を整理します。混同されやすい「ユーザーテスト」との違いも含め、基本的な考え方を押さえておきましょう。
定義
ユーザビリティテストとは、ユーザーが実際にプロダクトやサービスを操作してもらい、「使いやすさ」や「わかりやすさ」を評価する手法です。 対象ユーザーに近い属性の協力者にタスクの実行を依頼し、その操作の様子を観察することで、各画面や機能における操作のしやすさや導線の明瞭さなどを検証します。
ユーザビリティテストは開発の終盤で実施されるのが一般的ですが、設計やプロトタイプ段階から取り入れるのもおすすめです。初期のテストで得られた示唆をほかの機能開発にも応用することで、手戻りの工数を削減しつつ品質を確保することができます。
ユーザビリティテストの目的
ユーザビリティテストの目的は、開発者が気がつきにくい「ユーザー視点での使いやすさ」を検証することにあります。
仕様通り作動するとしても、実際のユーザー視点で「操作が直感的でない」「必要な情報になかなかたどり着けない」「誤操作が頻発する」といった問題が発生することは少なくありません。こうした問題は、ユーザーからの問い合わせやサポート対応の増加にもつながります。
ユーザビリティテストを行えば、設計者や開発者が見落としていた画面表示や操作手順のわかりづらさを発見しやすくなり、ユーザーがストレスなく使えるプロダクトに仕上げることができます。
UI/UXの向上は、満足度の向上や離脱率の低下につながり、CVR(コンバージョン率)やLTV(顧客生涯価値)といったビジネス指標の改善も期待できます。また、長期的には自社ブランドへの信頼性を高めるといった効果も見込めます。
ユーザビリティテストの種類と実施方法
ユーザビリティテストは、大きく2つの方法に分類できます。
ここでは、それぞれの手法の違いや、各手法におけるユーザー行動の観察方法について解説します。
実施形式
ユーザビリティテストの実施形式には、「ラボ型」と「リモート型」の2つがあります。
ラボ型
あらかじめ用意された検証環境にテスト対象者を招いて実施する形式
リモート型
対象者が自宅や職場など、実際の利用環境に近い場所から参加する形式
ラボ型では、観察者がその場で行動を見守ることができるため、視線の動きや操作の迷いといった細かな挙動を直接把握しやすいという特徴があります。さらに、機材やインターネット環境を事前に整備できるため、収集できるデータの精度も高くなります。
一方で、環境の準備や参加者の移動といった運営面での負荷がやや大きくなる点には注意が必要です。
リモート型は、移動の負担がないため、より幅広いユーザー層からの参加を募ることができます。また、日常に近い使用環境でのテストとなるため、より実践的な行動観察が可能です。その一方で、通信環境の影響を受けやすく、観察者が直接同席しないことで微細な反応をとらえにくくなるなど、非対面ならではの難しさも伴います。
| 実施形式 | 実施方法 | 主なメリット | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| ラボ型 | 会社が用意した環境にユーザーを招いて実施 | ・視線や操作の迷いなど、細かな挙動を直接観察できる ・高精度な記録機材を活用できる | ・操作手順が複雑で、微細な動きの観察が重要な業務システム ・セキュリティ上、外部に出せない社内ツール 例:医療機関向けの業務システムや金融機関の行内ツールなど |
| リモート型 | ユーザーが自宅や職場などの環境からオンラインで参加 | ・日常に近い使用状況でテストできる ・広範なユーザーから参加を募ることが可能 | ・利用シーンが多様なプロダクト ・全国各地のユーザーからフィードバックを得たい場合 例:生活者向けアプリやECサイト |
それぞれの形式にメリット・デメリットがあるため、テストの目的や対象プロダクトの特性に応じて、適切な実施形式を選択することが重要です。
観察手法
ラボ型・リモート型では、それぞれユーザーの行動や反応を観察・記録する方法が異なります。
ラボ型では、テスト担当者がユーザーのすぐ近くで観察できるため、視線の動きや操作の迷い、身体の動きなどを直接把握することが可能です。インタビューや発話思考法(操作中に考えていることや感じたことをその場で声に出してもらう手法)と組み合わせることで、行動の背景にある意図や感情も深掘りしやすくなります。
一方、リモート型では、画面共有や録画ツールを用いて操作の様子を記録・分析するのが一般的です。定性的な情報を収集したい場合には、チャットやビデオ通話によるコミュニケーションやアンケートを併用します。
このように、ラボ型・リモート型それぞれで観察手法が異なるため、必要な情報に応じて実施形式を選択することが重要です。
ユーザビリティテストの設計・実施・改善までのステップ
ここでは、ユーザビリティテストの設計から改善までのプロセスを整理します。
多くの人にとって身近な勤怠管理アプリを例に、シナリオ設計から評価・分析、改善アクションまでの流れを解説していきます。
シナリオとタスク設計のポイント
ユーザビリティテストでは、あらかじめ設定したシナリオに沿ってユーザーにタスクを実行してもらいます。テストの精度を高めるには、利用シーンに沿った自然な操作の流れを再現できるような設計が求められます。
例えば勤怠管理アプリの場合、次のようなタスクをテストに組み込むことが考えられます。
- 本日分の勤務時間を登録する
- 1週間分の勤怠を確認する
- 来週の有給休暇を申請する
実際の業務フローを意識したタスク設計により、ユーザーの自然な行動や思考を引き出すことができます。
また、タスクの難易度や所要時間、操作ステップの複雑さといった点にも配慮しながら、対象者に過度な負荷を与えない構成にすることも重要です。複数のユーザーに同様の条件で実施できるよう、再現性の高い設計を意識することで、比較可能なデータの収集にもつながります。
評価とデータ分析の手法
テストで得られた結果を分析するには、定量と定性の両面から多角的に評価を行う必要があります。
定量的な評価では、タスクの成功率や操作に要した時間、エラーの発生回数などを数値として記録します。これにより、複数のユーザーに共通する傾向や、仕様変更前後の比較が可能になります。
一方で、ユーザーの発話内容や操作中の戸惑い、意図しない行動といった要素は、観察や録画、発話思考法(操作の過程で感じたことを言語化してもらう手法)による定性分析によって明らかになります。
勤怠管理アプリの例であれば、定量・定性でそれぞれ次のような情報を収集することができるでしょう。
定量
・勤務時間入力に要する平均時間
・残業申請の操作ミス率
定性
・「保存ボタンの意味がわかりづらい」というアンケート結果
・勤務時間の入力中に画面を閉じてしまうユーザーが複数見られた(入力欄を探して迷う様子が観察された)
近年では、「ヒートマップ」と呼ばれる、クリックやマウス操作の履歴からユーザーが注目した箇所を色で示す手法や、クリックログなども活用されています。こうした技術を用いることで、ユーザーの操作傾向や躓きやすいポイントを視覚的に把握することができます。
問題点の特定と改善アクション
テスト結果から得られた示唆をもとに、具体的な改善アクションへとつなげていきます。
まずは、ユーザーのつまずきや混乱が生じた箇所を洗い出し、その背後にあるUI設計や情報設計の課題を特定します。次に、それぞれの課題に対して「発生頻度」と「ユーザー体験への影響度」という2つの軸で優先順位をつけ、限られたリソースの中で実行すべき改善内容を絞り込みます。
例えば、勤怠管理アプリの開発においてユーザビリティテストを実施した結果、次のような課題が明らかになったとします。
- 勤務時間の入力欄が見つけづらい
- 「保存する」というボタン文言が申請完了と誤解される
- モバイル画面で一部レイアウトが崩れる
この例であれば、申請漏れや誤操作といった業務上のトラブルにつながりやすい、「勤務時間の入力」や「保存ボタン」のデザインから優先して修正するとよいでしょう。
一方で、モバイル版のレイアウトの不具合については、勤務中のPCでの操作がメインなのであれば、上記2つよりも優先度を下げることができます。
ユーザビリティテストで発見された課題の整理(勤怠管理アプリの例)
| 発見された課題 | 発生頻度 | 影響度 | 影響度 |
|---|---|---|---|
| 勤務時間の入力欄が見つけづらい | 高 | 中 | 高 |
| 勤務時間の入力欄が見つけづらい | 中 | 高 | 高 |
| モバイル画面で一部レイアウトが崩れる | 低 | 低 | 低 |
改善施策の検討にあたっては、デザイナーや開発者、プロダクトマネージャーなど複数のメンバーが連携し、課題の背景や解決方針を共有することが不可欠です。改善案を実装し、再度テストによって仮説を検証するというサイクルを通して、より質の高いユーザー体験へとつなげることができます。
ユーザビリティテストで“使いやすい”プロダクトを実現する
ユーザビリティテストは、ユーザー満足度に直結する問題を特定できる重要なプロセスです。
ユーザーに近い人物の行動や反応に基づいて課題を抽出し、改善を積み重ねていくことで、機能の過不足や設計上のボトルネックを早期に把握することができます。これによって、開発リソースの浪費を最小限に抑えつつ、満足度の高いプロダクトを実現することができます。
一方で、ユーザビリティテストには特有のノウハウが求められるため、社内にテスト専門の人材がいない場合、観点の漏れや体制設計の不備が生じることも少なくありません。
テストの設計や評価項目の設定、実施体制の整備に課題を感じている場合には、専門的な知見を持つ第三者の支援を活用することも有効です。
AGESTでは、ユーザビリティテストを含めたテストの設計・実施から評価、改善提案までを一貫して支援するサービスを提供しています。現場の課題に即した実践的な改善提案を通じて、品質と開発効率の両立をサポートします。
自社に適した品質保証体制の確立を目指す方は、ぜひ以下のページをご覧ください。